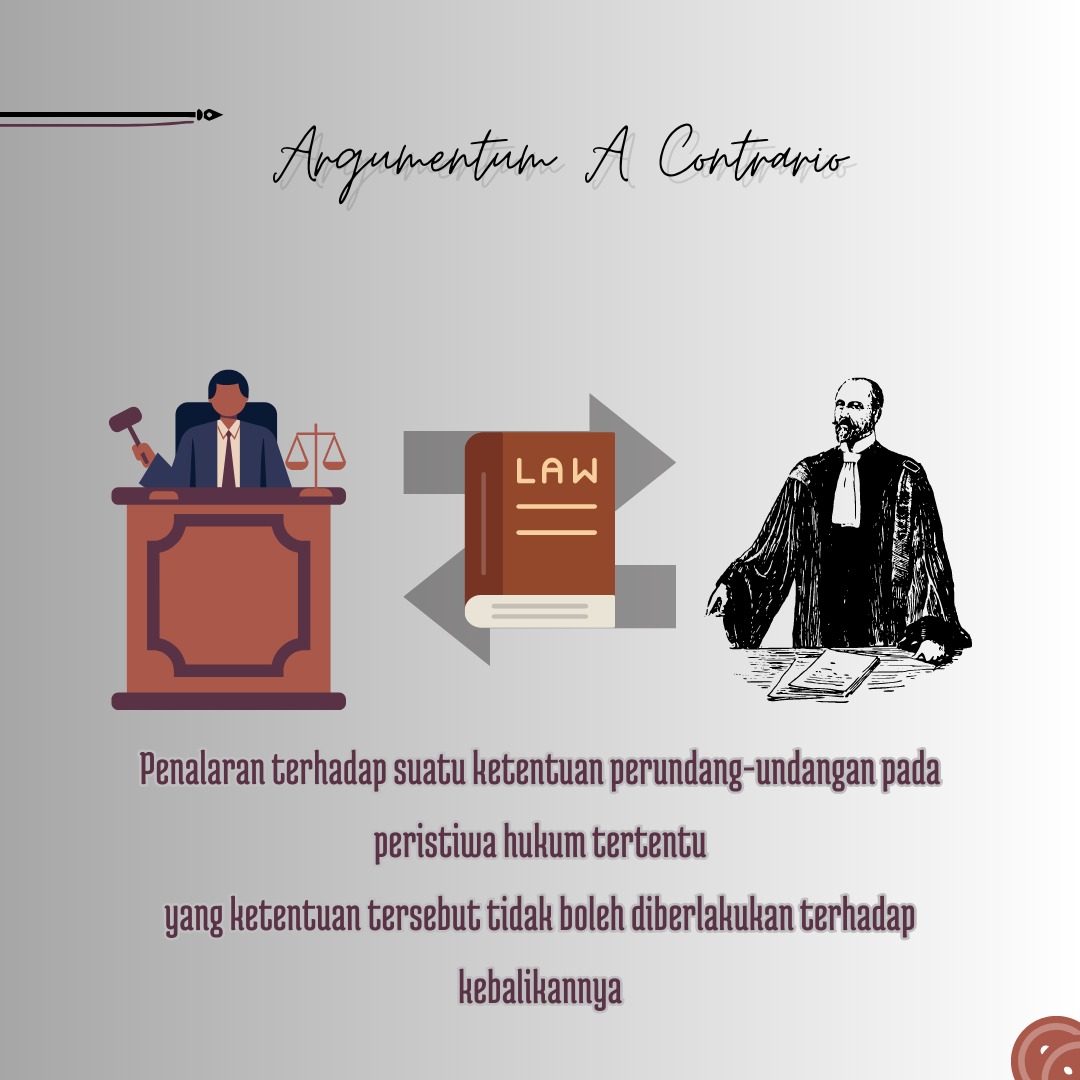
法的発見(rechtsvinding)は、事件の判断において法律が明確でない場合、裁判官によって行われなければなりません。さらに、司法権法第10条第1項は、裁判官が事件を却下することを禁じています。その結果得られた法的発見は、法律または裁判官の参考資料、すなわち判例となります。推論を用いる法的発見の一つに、反論があります。
逆説的論証は、しばしば「逆説的」とも呼ばれ、遭遇した具体的な出来事と法律で規制されている出来事との間の対照的な理解に基づいて法律を解釈または説明することです。
反対の開示の解釈を理解する
提起された問題に関連して、法律を矛盾した方法で解釈することは、反論(argumentum a contrario)としても知られています。この点に関して、R. Soeroso の著書『法学入門』(115 ページ)は、次のように述べています。
反論とは、否認に基づく法律の解釈であり、つまり、問題と法律の特定の条項で規定されている問題との間に矛盾があることを意味します。
R. Soeroso 氏はさらに、この拒否は、問題となっている事項が問題の記事には含まれておらず、法定規制の範囲外であるという結論に基づいていると説明した。
一方、スディクノ・メルトクスモ氏は、逆説は事象の非類似性を強調するものだと説明した。ある事象が法律で具体的に規定されていないにもかかわらず、その反対の事象が法律で規定されている場合がある。この場合、法律の適用を求めている事象については具体的な規定が存在しない。その代わりに、法律の適用を求めている事象と同一ではないものの、類似点を持つ別の事象については具体的な規定が存在する。
さらに、対比解釈は本質的に類推解釈と同じであり、結果が逆になるだけです。類推は肯定的な結果をもたらし、対比解釈は否定的な結果をもたらします。対比論に基づく解釈は、法律または立法の定式化を狭めます。その目的は、法的確実性をさらに強調し、疑義を回避することです。また、前述のとおり、インドネシア刑法第1条第1項により、刑法では類推は認められていません。ポンペ氏が述べているように、類推は禁止されていませんが、依然として裁判官の判断に委ねられています。
類推によって法律を使用することと、反論に基づいて法律を使用することの違いは次のとおりです。
• 法則を類推適用すると肯定的な結果が得られますが、逆説的に適用すると否定的な結果が得られます。
• 法律を類推使用することは、法律規定または法定規制の有効性を拡大することを意味します。一方、反論を使用することは、法定規定の有効性を狭めることを意味します。
法を類推的に使用し、反論に基づく式は次の通りである。
類推法と反論法はどちらも法解釈に基づいています。どちらの方法も問題解決に活用できます。どちらの方法も、法律の条項が問題に対応していない場合に適用されます。どちらの方法も、法律の空白を埋めることが目的です。
議論 A Contrario の解釈の例
民法第34条は、女性は夫との離婚後300日という一定期間を経過するまで再婚できないと規定している。しかし、ア・コントラリオ(逆説)論に基づき、この規定は男性には適用されない。ヨーロッパの民法の原則によれば、女性は300日が経過するまで再婚を待つ必要があるが、イスラム法では、この期間中に前の夫からの相続財産が残っている可能性を懸念し、イッダ期間を純潔期間の4倍である100日と定めている。女性がイッダ期間を経過する前に結婚した場合、次の夫との間に生まれた子供の身分は不明確となる。
最後に、上記の説明から、次のように結論付けることができます。
新しい(現代的な)見解によれば、既存の法は不完全であり、社会で生じるすべての法的事象を網羅することはできない。したがって、裁判官は法の発見に関与する。パウル・シャルテン教授はこれを「Recht vinding(法的根拠の発見)」と呼ぶ。
裁判官は法律を見つけるのに協力しますが、立法権はありません。
言い換えれば、反論(argumentum a contrario)に基づけば、問題となっている問題は同条の規定に含まれていないため、この規定は男性には適用されないと言える。民法第34条は男性に関する言及はなく、女性に特化している。
もう一つの例を挙げると、民法第1320条に規定されている正当事由の定義は、詳細かつ具体的に説明されていません。しかし、民法第1337条は、禁止事由を「法律、道徳及び公の秩序に抵触するもの」と定義しています。したがって、逆に言えば、正当事由とは、法律、道徳及び公の秩序に抵触しない事由であると結論付けることができます。